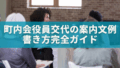秋の味覚といえば、やっぱり松茸ですよね。
スーパーやデパートの食品売り場に並びはじめると、季節の訪れを感じて「もう秋なんだなぁ」と思う方も多いのではないでしょうか。
香り高く、見た目にも存在感のある松茸は、秋のごちそうの代名詞とも言える存在です。
でも中には、「なんだか香りが強すぎて苦手かも…」「ちょっとくさい気がする」と思ったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?むしろ、せっかくの高級食材にもかかわらず「自分には合わないな…」と感じてしまったという体験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
実は、松茸の香りに対して「くさい」と感じる人も少なくないんです。
松茸は日本を代表する高級食材として知られていて、「香り松茸」とまで言われるほど、その香りが評価されています。
それにもかかわらず、どうして人によっては不快に感じることがあるのでしょうか?
香りというのはとても主観的なものです。
ある人にとっては「自然を感じる豊かな香り」でも、別の人にとっては「湿った土のにおい」「かびっぽい香り」と感じることもあります。
この記事では、松茸の香りを「くさい」と感じる理由について、科学的な要因、嗅覚の個人差、文化的な背景、さらに香りが苦手な方でも松茸を楽しめる調理法や代替の食材などもやさしく丁寧にご紹介していきます。
松茸初心者の方でも安心して読める内容にしていますので、これをきっかけに“香りの感じ方”をもっと自由に、前向きに捉えられるようになるかもしれません。
ぜひ最後までお付き合いくださいね。
松茸の香りが苦手な人は意外と多い?|SNSや口コミに見るリアルな声

「松茸って高級なのに、香りがちょっと苦手…」そんな声をSNSやレビューでよく見かけます。
中には「靴下っぽい」「土のにおいが強すぎる」「森の落ち葉のようなにおいで食欲がなくなる」といった意見もあり、思ったよりも否定的な印象を持っている人が多いことがわかります。
ネット上の反応はさまざま
実際にSNSでは、
- 「家族は好きだけど私は無理…」
- 「子どもが“変なにおい”って言ってた」
- 「毎年食卓に出るけど、私は香りでギブアップ」
- 「高級なのは知ってるけど、どうしてもにおいが好きになれない」
といった投稿が見られ、香りに対する好みの差がかなりあることがわかります。
人によっては、松茸の香りが食欲をそそるどころか、逆に食欲を減退させることもあるようです。
アンケート結果でも“苦手派”は一定数
ある調査では、松茸の香りを「くさい」と感じた人が3〜4割近くいるという結果も出ています。
しかも、そのうちの多くが「香りの強さが気になる」「香ばしさではなく土っぽさが前面に出る」といった理由を挙げていました。
このように、松茸は「高級=誰もが好きな香り」と思われがちですが、実際には意見が大きく分かれる食材です。
そのため、香りが合わないと感じることは決して珍しいことではないんです。
松茸の香りはなぜ高級とされるのか?|「いい香り」とされる理由を解説

松茸は「香り松茸、味しめじ」と言われるほど、その香りが評価されています。
香りの良さが松茸の魅力の一つとされ、贈答品や高級料理の食材としても重宝されています。
香り高い松茸料理が出てくるだけで、特別感や季節感を感じるという方も多いですよね。
でも、なぜ松茸の香りは“いい香り”とされ、そこまで価値があると考えられているのでしょう?その背景には、香りの成分そのものの特徴や、日本の食文化、そして「希少性」の影響など、さまざまな要素が関わっています。
香りを評価するという感覚は、単に嗅覚だけの問題ではなく、私たちの経験や記憶、文化的背景にも深く結びついているんです。
ここからは、松茸の香りがどうして「良い香り」として愛されてきたのか、もう少し掘り下げてご紹介していきます。
森や土を感じさせる香り
松茸の香りには「秋の森」「土の湿気」「自然の深み」など、自然をそのまま閉じ込めたようなニュアンスを感じる人が多くいます。
その香りは、まるで落ち葉が積もった林道を歩いているときのような、どこか懐かしくて優しい空気感を思い起こさせてくれます。
特に日本人にとっては、自然と調和する感覚や、季節の移ろいを五感で感じることが大切とされる文化があるため、このような素朴で複雑な香りに対して「癒し」や「豊かさ」を見出す傾向があります。
また、松茸の香りは香水のように“つくられた”ものではなく、天然そのもの。
だからこそ、人工的な香りに慣れている現代人にとっては最初こそ戸惑うことがあるかもしれませんが、一度魅力に気づくと「自然の贅沢さ」を感じさせてくれる特別な存在になるのです。
高級=美味しいというイメージも影響
松茸は非常に希少で、国内では採れる量も限られていることから「高級食材」として位置づけられています。
この「希少=価値がある=美味しい」といった心理的なバイアスが、松茸の香りへの評価にも影響していることが考えられます。
たとえば、高価なワインやチーズも、初心者にとっては香りが強すぎたりクセがあると感じることがありますが、「高いから良いものに違いない」という意識がその体験をポジティブに変える場合もあります。
松茸もまた、「高級感」や「季節感」といったストーリーとともに語られることで、その香りが特別なものとして受け入れられている側面があるのです。
松茸が「くさい」と感じる原因とは?|香り成分と嗅覚の個人差から解説

実は、松茸の香りがくさいと感じるのには、しっかりとした科学的な理由があるんです。
香りというのはとても主観的な感覚ですが、その裏には化学的な成分や、個人差に関わる要因が関係しています。
香りの成分「マツタケオール」とは
松茸の独特な香りの正体は「マツタケオール」という成分。
この成分は、土や木、皮のような自然に由来するにおいと表現されることが多いです。
中には「湿った落ち葉」や「古木のような香り」と感じる人もいます。
マツタケオールはごく微量でも強く感じられる成分で、香水や香料として人工的に再現されることもあるほど。
ですが、この自然的な香りは人によって「深みがあって落ち着く」と感じることもあれば、「かび臭い」「カビた木材のにおい」とネガティブに捉える場合もあるのです。
嗅覚の違いには個人差や遺伝も関係
香りの感じ方は、本当に人それぞれです。
遺伝子によって嗅覚の感受性が異なることがわかっており、あるにおいに敏感な人もいれば、まったく気にならない人もいます。
また、小さい頃からの食体験や生活環境によって「良い香り」と感じる基準も変わってきます。
たとえば、自然の中で育ってきた人は、土や木の香りに懐かしさや安らぎを感じやすい傾向にあります。
一方で、都市部で暮らし、人工的な香りに慣れている人は、こうした自然由来の香りを“異臭”として捉えてしまうこともあるのです。
体調や気分によっても変わることが
さらに、同じ香りでも、そのときの体調や気分によって感じ方が大きく変わることもあります。
空腹のときや疲れているとき、ストレスが溜まっているときには、においに対して敏感になったり、不快に感じやすくなったりします。
たとえば、普段は気にならなかった香りでも、「今日はちょっときついかも…」と感じる日ってありますよね?松茸の香りも同じように、体の状態や精神的なコンディションによって印象が変化する可能性があるんです。
このように、松茸の香りが「くさい」と感じられる背景には、成分の特性だけでなく、嗅覚の個人差、生活経験、そしてその日のコンディションまで、さまざまな要素が関わっているのです。
他のきのこと比べて松茸は本当に独特?|しいたけ・ポルチーニとの比較
松茸の香りが苦手な方は、他のきのことの違いを知ると少し納得できるかもしれません。
実際に比べてみると、松茸の香りがいかにユニークで特別な存在なのかがよく分かります。
他のきのこたちが持つ香りと比べて、松茸がなぜ“くさい”と感じられてしまうのか、その理由も見えてきます。
香りの方向性が全然違う!
例えば、しいたけは旨味が強く、加熱することで「だし」のような風味が際立つきのこです。
日本料理の基本とも言える和風だしのベースになるため、私たち日本人にはとてもなじみ深い香りとして親しまれています。
一方、ポルチーニはイタリア料理などでよく使われるきのこで、乾燥させるとナッツやチョコレートに似た甘く香ばしい香りが出るのが特徴です。
このように、しいたけもポルチーニも「旨味」や「甘み」を伴う香りを持っており、どちらも比較的好まれやすい方向性のにおいです。
それに対して、松茸はもっと自然で素朴な香り。
たとえるなら、落ち葉が積もった山道のにおいや、濡れた苔のような空気感。
こうした香りは人工的な香料に慣れた人にとっては“野性的すぎる”“土臭い”と感じられてしまうことがあるのです。
世界の中での松茸の評価
海外では、松茸は必ずしも「香りが良いきのこ」として評価されているわけではありません。
むしろ、日本独自の文化や風土が育んできた“特別な食材”という側面が強いのです。
例えば、北米やヨーロッパの一部では、松茸の香りを「古い布」「濡れた靴」「靴下のにおい」と表現する人もいるほど。
もちろん、すべての人がそう思っているわけではありませんが、少なくとも日本ほど一様に高評価されているわけではないのです。
ただし、最近では日本食ブームの影響もあり、松茸の希少性や“日本らしさ”が再評価されつつあるのも事実。
文化的な価値が付加されて「ユニークな高級食材」として扱われるようになってきています。
このように、他のきのこと比較することで、松茸の香りの特徴がよりはっきりと見えてきます。
特に「なぜ自分には松茸の香りが強く感じるのか」と疑問に思っていた方には、香りの方向性や文化的背景を知ることで少し気持ちがラクになるかもしれません。
松茸の香りが苦手でも楽しめる!おすすめの食べ方と工夫
香りが苦手でも、ちょっとした工夫で松茸を美味しくいただけることがあります。
無理に我慢して食べる必要はなく、自分のペースで楽しむことが何より大切です。
ここでは、松茸の香りを和らげる調理法や、香りが控えめな代替食材を使ったアイデアをご紹介します。
香りが控えめになる調理法を選ぶ
松茸の香りが苦手な方には、水分をたっぷり使った調理法がとてもおすすめです。
たとえば、炊き込みご飯や土瓶蒸し、茶碗蒸しなどは、熱と水分が香りをほどよく飛ばしてくれるため、松茸特有の香りがまろやかに感じられます。
特に炊き込みご飯は、ご飯の甘みや出汁の風味と合わさって香りが全体に溶け込むので、「香りが苦手でも美味しく食べられた!」という声も多いです。
土瓶蒸しは、松茸以外の具材の旨味も加わることで、香りに対する抵抗感が軽減される効果があります。
逆に避けた方がよいのは、焼き松茸やホイル焼きといった調理法です。
これらは松茸の香りをダイレクトに楽しむ料理のため、香りが強く立ちすぎてしまう傾向があります。
初めての方や香りに敏感な方は控えめにしておくと安心です。
代替食材を使うのもアリ
「香り松茸 味しめじ」という言葉があるように、香りが苦手な方には、味わいで楽しめるきのこを選ぶのも賢い選択です。
しめじやエリンギ、まいたけなどはクセが少なく、食感もよくて料理にも使いやすいきのこです。
特にエリンギは、バターやにんにくと炒めるだけで香ばしさが増し、香りに敏感な方でも食べやすくなります。
また、しめじは煮物や鍋料理にぴったりで、全体に旨味を広げてくれる存在。
無理をして松茸を使わなくても、こうした食材で十分に秋の味覚を楽しむことができますよ。
「自分の好みに合わせて選ぶこと」が、食を楽しむうえでとても大切です。
香りが苦手でも工夫次第で美味しく味わえる方法はたくさんありますので、ぜひ気負わずチャレンジしてみてくださいね。
松茸の香りは悪くない?|「くさい=不快」ではないという考え方
香り=不快とは限りません。
むしろ「独特な香り」こそが、松茸の最大の魅力だと考える人もたくさんいます。
他の食材にはない深みや、自然の気配を感じさせてくれるその香りは、料理に“特別な瞬間”を添えてくれる存在でもあるのです。
発酵食品も「におうけど美味しい」ものの代表
たとえば納豆やブルーチーズ、キムチ、くさやなど、においが強烈でも多くの人に愛されている発酵食品ってたくさんありますよね。
それらは、初めて口にしたときには驚くような香りでも、慣れてくると「クセになる味わい」として高く評価されるようになります。
松茸の香りも、そうした食材と同じように「最初は戸惑ったけれど、今ではこの香りがないと物足りない」と感じるようになる方が多いんです。
料理の世界には、「におい=悪いもの」とは限らないどころか、香りそのものが“美味しさの一部”になっているケースがたくさんあるんですね。
香りの好みも十人十色
もちろん、すべての人が松茸の香りを好きになる必要はありません。
「みんなが美味しいって言ってるから」「高いものだから頑張って食べなきゃ」と無理をする必要もないんです。
大切なのは、自分の感じ方を大事にすること。
香りの好みは人それぞれですし、ある食材が苦手だからといって食の楽しみが減るわけではありません。
もし松茸が合わないと感じたら、それはそれで素敵な“あなたらしい感性”なのです。
香りを楽しむ方法も食べ方も自由です。
無理せず、気になるものだけを選びながら、自分なりの食の世界を広げていきましょう。
まとめ|松茸の香りが苦手でもOK!嗅覚や味覚は人それぞれで正解も自由
松茸の香りがくさいと感じても、それはまさにあなたの感性が豊かだからこそ。
食べ物の好みや感じ方は、個性のひとつであり、誰かと比べて「正解・不正解」があるものではありません。
香りに敏感な人もいれば、においに対してあまり気にならない人もいます。
それぞれの感じ方があるからこそ、食の世界は多彩で楽しいものになるのです。
無理に「みんなが好きだから自分も好きにならなきゃ」と思う必要はまったくありません。
自分の味覚や嗅覚に素直になることで、もっと気軽に、もっと心地よく食事を楽しむことができます。
松茸が合わないと感じたときは、香りの穏やかな調理法を試したり、代わりにしめじやエリンギなど他のきのこを使って、秋の味覚を自分なりの方法で取り入れてみましょう。
季節の恵みは無理して楽しむものではなく、心地よい形で味わうことが大切です。
周りの評価や常識にとらわれず、自分の「おいしい」と思える感覚を大事にして、あなたらしい秋の楽しみ方を見つけてくださいね。