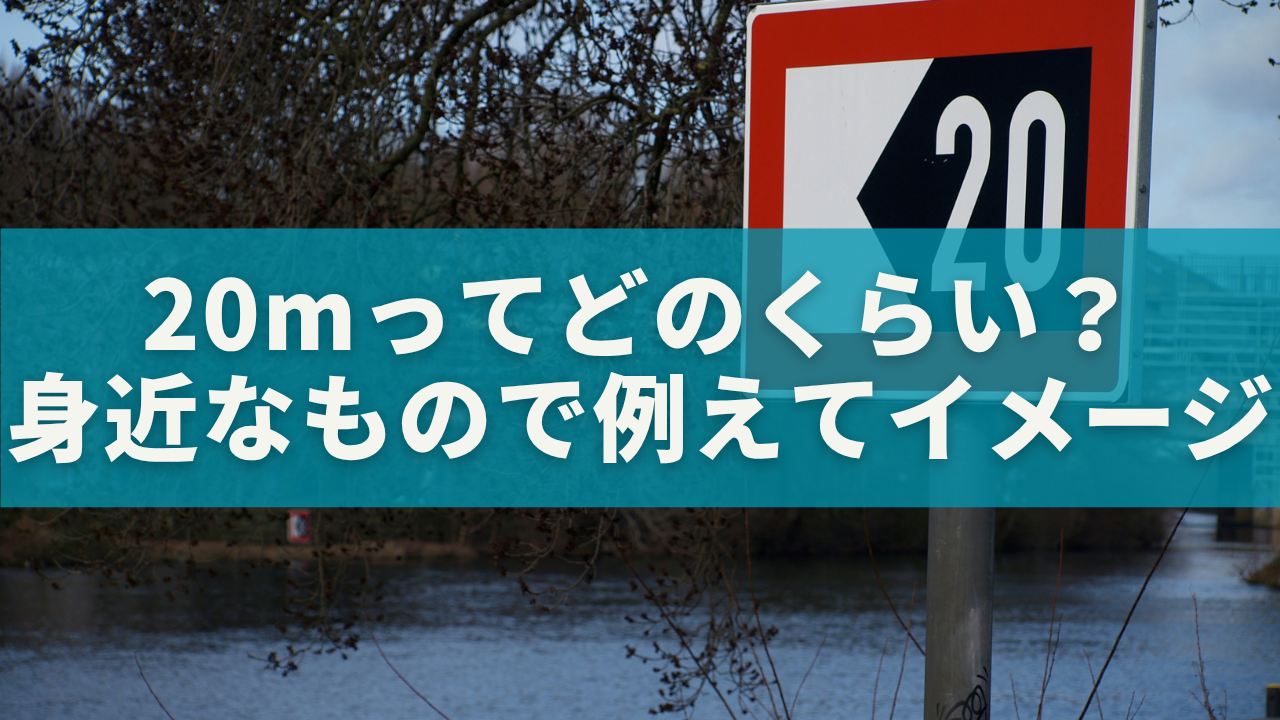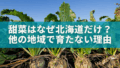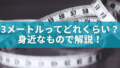「20メートル」と聞いて、どのくらいの高さや長さかパッとイメージできますか? 数字としては知っていても、実際にどんなものと同じくらいなのか、なかなか想像しづらいですよね。
この記事では、そんな「20m」の距離感をわかりやすくお伝えするために、建物・乗り物・動物・スポーツ施設など、身近なものを使って具体的に解説していきます。
特に女性やお子さん、数字に苦手意識がある方でもイメージしやすいように、やさしい言葉でお届けします。 「高さ」「長さ」の感覚をつかむことで、日常の中でも役立つ距離感が身につきますよ。
それでは、一緒に「20mってどんな感じ?」を楽しく学んでいきましょう♪
20mの長さ・高さはどれくらい?まずは一言でイメージしよう
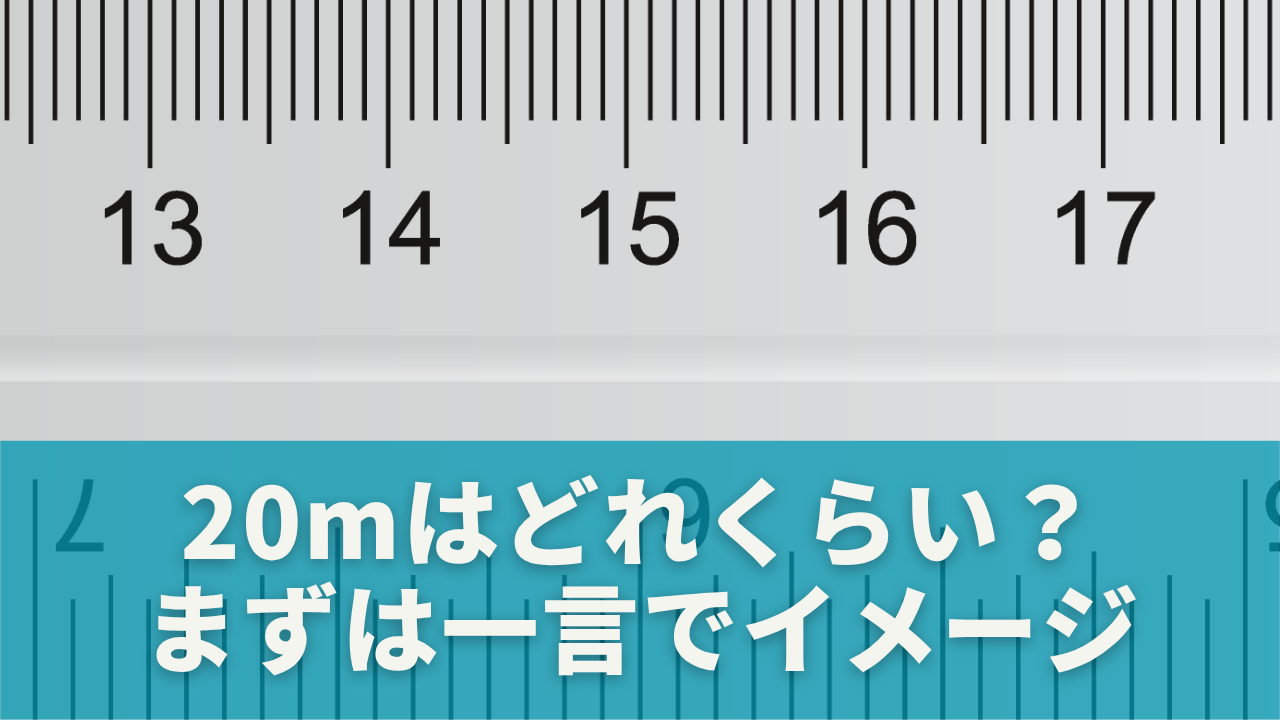
数字だけでは伝わらない「20m」の感覚とは
20mと言われても、パッとその距離や高さを思い浮かべるのはなかなか難しいですよね。特に、普段からメートル単位で物の大きさを意識することが少ない方にとっては、「なんとなく長そう」「高そう」といったあいまいなイメージしか持てないかもしれません。たとえば、買い物や通勤のときに「何メートル歩いた」なんて考えることって、あまりないですよね。
女性の方やお子さんにとっては、数字よりも「見たことがあるもの」や「体験したことのあること」に置きかえてあげたほうが、ずっとイメージしやすくなります。ですから、まずはその感覚を「数字」から「感覚」に変えてあげるのがポイントです。
結論!20mはこんなに高い・長い
20mは、ざっくり言えば「6〜7階建ての建物」と同じくらいの高さになります。建物で言えば、見上げると首が痛くなりそうなくらいの高さですね。そして長さでいえば、歩くと約30歩ほど、走るとほんの数秒で到達できる距離です。お散歩中に少し先に見える電柱までの距離、そんな風にイメージしてみてください。こうして考えると、なんとなく「遠すぎず近すぎず、でも結構な長さなんだな」と感じられるのではないでしょうか。
建物や階数でわかる「20m」の高さとは
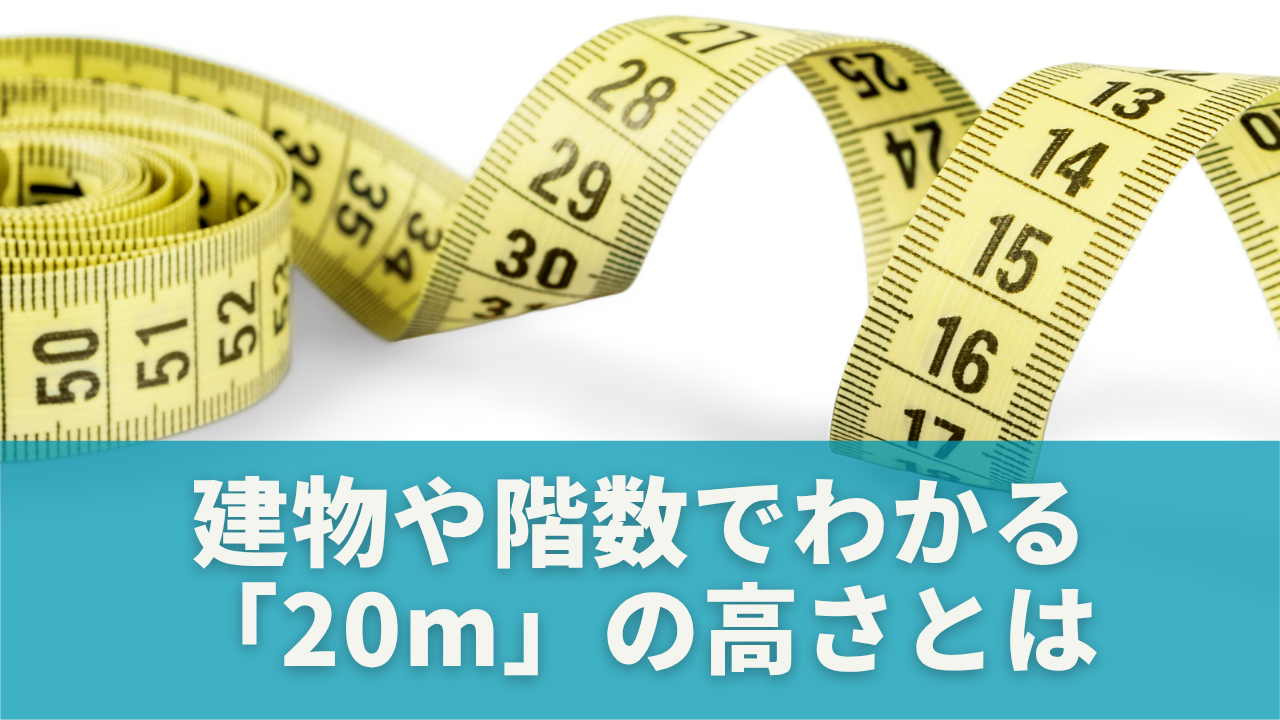
一般的なマンションなら何階分?
マンション1階の高さはおよそ3mが目安です。これは天井の高さに加え、床や構造部分の厚みなどを含めた平均的な数字です。ですので、単純計算で20mは6〜7階分に相当します。「あのマンションの上の方くらいかな?」とイメージしてみてくださいね。マンションの上層階は風通しも良く、見晴らしがよかったりしますよね。そんな場所の高さを思い浮かべてみると、「20mって、案外高いんだな」と感じられるかもしれません。
ちなみに、最近では1階の天井を高くしたデザイン性の高いマンションもあり、その場合は5階で20mに達することもあります。構造や設計によっても高さの感じ方が少し変わるんですね。
学校の校舎・電柱・観覧車との比較
小学校の校舎だと、3〜4階建てが一般的です。その高さが約12〜15mくらいになりますので、20mというのはそれよりもひと回り高い高さになります。校庭から見上げる校舎の屋上に、さらに1階ぶんプラスしたようなイメージです。
また、電柱も高さの参考になります。通常の電柱は約10〜13mほどですが、幹線道路沿いなどでは20m近いものも存在します。見上げるとかなり高く感じますよね。さらに、遊園地にある小さめの観覧車もだいたい20m前後の高さで作られているものが多くあります。観覧車の頂上から景色を眺めたときの視点が、ちょうど20mの高さにあたるわけです。そう考えると、視覚的な体験からも20mをイメージしやすくなりますね。
20mの長さを身近なもので例えると?
動物や乗り物で20mを実感しよう
20mは、たとえばキリンが4頭並んだくらいの長さです。キリンの体長は1頭あたり約5m前後ですから、それが4頭並ぶとちょうど20mになります。動物園でキリンを見たことがある方なら、その迫力ある体をイメージすることで、ぐっと現実味のある距離感がつかめると思います。
また、20mという距離は、新幹線の1車両(約25m)より少し短いくらいです。ですので、新幹線に乗ったことがある方は、ホームに停まっている車両の全体を思い浮かべながら「これよりちょっと短いな」と考えてみてください。他にも、普通の電車の1車両(通勤電車など)は約20mなので、毎日使っている電車の長さそのものと思うと、さらに身近ですよね。
飛行機の主翼の長さにも近いものがあり、小型機の翼幅は20m前後の場合もあります。空港などで飛行機を見かけたことがあれば、そのスケール感とも重ねられるかもしれません。
テニスコート・バスの長さと比べると?
テニスコートの長さは約24mですので、20mはその端から少し手前、サイドライン付近までの長さです。実際にスポーツをされている方は、試合中に走る距離として「ちょっと長い1往復」くらいに感じるかもしれませんね。
また、観光バス1台の長さは約12m前後です。20mはちょうどバス1.5台分ほどなので、高速道路のサービスエリアなどで並んで停まっているバスを2台見比べると、長さのイメージがしやすくなります。さらに言えば、宅配トラック(大型)や消防車などの特別車両も10〜12mほどですので、そういった乗り物を使った比較もおすすめです。
日常の中で見かけるものに置き換えることで、数字だけではつかめなかった20mのスケールが、より立体的に感じられますね。
有名な建造物やモニュメントと比べる20m
札幌市時計台・道頓堀グリコサインと同じくらい?
札幌市時計台の高さはおよそ19.8m。つまり、20mとほぼぴったり同じくらいの高さということになります。札幌の観光名所として知られるこの建物を思い浮かべると、「20m」という数字に現実感がわいてきますよね。時計台は歴史ある建物でもあり、その堂々とした佇まいを見上げたときの感覚が、まさに20mの高さです。
大阪の道頓堀にある有名なグリコサインも、同じく20m近い高さを誇ります。観光地でよく写真におさめられるこの巨大な看板、実はかなりのスケール感なんですよ。夜にはライトアップされて一層存在感を増すその姿を思い出すと、「あの看板と同じくらいの高さなんだ」とイメージしやすくなるのではないでしょうか。
どちらも日本人なら一度は目にしたことがある、もしくはテレビや雑誌などで見かけたことのある有名なスポットなので、20mという高さの実感にぴったりです。
奈良の大仏・実物大ガンダムで高さを体感!
奈良の大仏(像本体)は約15m、台座を含めると18mほどあります。大仏を間近で見上げたとき、その圧倒的な存在感に驚かれた方も多いのではないでしょうか。それよりも少しだけ高いのが20m。つまり、大仏のてっぺんにあと少し何かを乗せたら20mになる、そんな高さです。
そしてもうひとつ、迫力でいえば負けていないのが実物大ガンダム。お台場や横浜で展示されたことのある等身大のガンダムは、およそ18〜19mの高さがあります。SFの世界から飛び出してきたようなロボットのスケールを体感したことがある方なら、その大きさに20mという数字が重なって感じられるはずです。
こうした有名モニュメントやキャラクター像との比較は、数字だけではつかめない高さを、感覚的にわかりやすくしてくれますね。
遊具やスポーツ施設の高さでイメージしやすく
飛び込み台・滑り台・クライミング施設の高さは?
20mの高さは、競技用の高飛び込み台(通常10m)の約2倍ほどになります。つまり、もし10mの飛び込み台に立ったときに「怖いな」と感じたことがあれば、その倍の高さが20mだということです。水に飛び込むときの緊張感や風の感触を思い出せば、20mという高さの迫力がよりリアルに伝わるかもしれません。
また、遊園地にある滑り台の中でも特に大型のものや、フリーフォール型のアトラクションなどは、およそ15〜20mの高さがあります。滑り降りる瞬間のドキドキや、地上を見下ろす時のスリルは、まさに「20mならでは」の体験と言えるでしょう。
ボルダリングジムや屋外のクライミング施設にも、20m前後の高さの壁があります。最上部にたどり着いたときの達成感や、ふと足元を見下ろした時のスリルも、20mの高さならでは。体を動かすアクティビティと組み合わせて想像すると、とても実感しやすいです。
バンジージャンプの高さは20mが定番って本当?
はい、実はその通りです。バンジージャンプの中でも、初心者向けや体験コースとしてよく採用されているのが20mの高さです。ジャンプ台に立つと、思っている以上に「高い…!」と感じる方が多く、最初の一歩を踏み出すのに勇気がいる高さです。
20mというと、安全性も確保されながら十分なスリルを味わえる絶妙な高さとされており、国内外のバンジージャンプ施設で定番となっています。もし挑戦したことがある方は、その時の風景や心拍数を思い出してみてください。まだ体験したことがない方も、動画やテレビなどで見た場面を思い浮かべれば、20mのスケールがよりリアルに感じられるはずです。
時間でイメージ!20mを歩く・走ると何秒?
20mを徒歩で歩くとどのくらいの時間?
大人が普通の速さで歩くと、20mは約15秒ほどかかります。この時間は、周囲の景色を少し眺めながらゆったり歩いた場合の目安です。もし少し急ぎ足になれば、10秒以内で歩けるかもしれませんね。
たとえば、自宅の玄関から少し離れた郵便ポストまで、コンビニの店内で飲み物コーナーからレジまで歩くくらいの距離が、ちょうど20m前後です。「えっ、そんなに短いの?」と思われた方もいるかもしれません。実際に歩いてみると、想像していたよりもあっという間に着いてしまう距離なんです。
また、日常生活で「ちょっとそこまで」と移動する距離が、意外と20m前後であることも多いんですよ。小さなお子さんと手をつないで歩いたり、スーパーでお買い物カートを押しながら移動したりといった場面で、「これくらいかな」と実感していただけると思います。
運動場やかけっこで「20m」を体感しよう
学校の体育でよく登場するのが50m走。その半分以下となる20m走は、まさに「ちょっとダッシュ」するのにぴったりな距離です。元気いっぱいなお子さんであれば、5秒以内で駆け抜けてしまうくらい。足の速い子なら3〜4秒ほどでゴールしてしまうことも。
また、運動場や公園で親子でかけっこをするとき、「20m先にある木まで競争しよう!」なんて遊び方もおすすめです。目標物を設定すると、自然とその距離感が身体で覚えられますよね。
スポーツに親しんでいる方であれば、20mという距離はスプリント練習やウォームアップなどでもよく使われます。短いけれども、全力で動けば意外と体に負荷がかかる距離。それだけ「ちょうど良い長さ」として使いやすいんですね。
子どもに20mをわかりやすく説明する方法
小学生に伝えるにはこう教えるとわかりやすい
「20mは教室5つ分くらいだよ」と伝えると、小学生にもぐっとイメージしやすくなりますよね。子どもたちは数字そのものよりも、自分が日常的に過ごしている空間や目で見て触れたことのあるものに置きかえてもらうほうが、ずっと理解しやすくなります。
たとえば、「20mは大きなシャチが2頭分並んだくらいだよ」や「サッカーのゴールラインの長さよりちょっと短いよ」といったように、興味を持っているスポーツや生き物に例えるのも効果的です。さらに、「運動会のかけっこで走る距離の半分ちょっとだよ」と伝えると、体験と結びついて距離の感覚がグッとリアルになります。
教室の机を数えて、「1列分でどのくらいあるかな?」「あと何列分で20mになるかな?」とクイズのように考えさせるのも、楽しみながら学べる工夫のひとつです。
家庭学習や自由研究にもおすすめの伝え方
20mという距離は、家庭学習や自由研究のテーマとしてもとても使いやすい素材です。たとえば、巻き尺やメジャーを使って実際にお庭や近くの公園で20mを測ってみると、数字ではわからなかった距離感が体でつかめます。「思ったより短い!」「こんなに長いんだ!」という反応が返ってくることも。
また、紙テープや毛糸などで20mの長さを作って、玄関からどこまで届くか、部屋の中でどのくらいの長さかを一緒に確かめてみるのもおすすめです。色を塗ったり飾ったりすれば、作品としても楽しくなりますし、観察レポートにもつなげられます。
さらに、写真を撮って記録を残したり、身近なものと比較して一覧にしたりすれば、自由研究のまとめとしても十分に立派な内容になりますよ。家族で一緒に楽しめる体験型学習として、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
20mをどうやって測る?身近な測定方法と便利グッズ
メジャー・レーザー距離計の使い方
長い距離を測るには、やはり巻き尺(メジャー)が便利です。一般的な家庭用のメジャーは5m〜10mが多いですが、20mを測るには「巻き取り式」の長尺メジャーがおすすめです。柔らかいテープ状のものや、しっかりとしたスチールタイプもありますので、目的に応じて使い分けると良いですね。
特に屋外での測定や、複数回距離を測りたいときには、数字の視認性や巻き取りやすさもポイントになります。また、ひとりで測る場合には、地面にメジャーを固定できるようなピン付きのタイプだと、安定して測ることができますよ。
さらに便利なのが、レーザー距離計。最近では手のひらサイズで軽量なモデルが増えており、ボタンを押すだけで直線距離を測定してくれるため、時間も手間も省けます。建築現場やインテリアのレイアウトだけでなく、日常でも使える場面が多く、アウトドアやDIYにも活躍します。
スマホアプリや目測で簡単に距離をつかむコツ
スマホにも、距離を測るための便利なアプリがいくつか登場しています。iPhoneであれば「計測」アプリ、Androidにも似たようなAR機能付きのアプリがあります。画面上に表示されるガイドラインに沿ってスマホを動かすだけで、だいたいの距離がわかるという手軽さが魅力です。
ただし、正確さを求めるにはある程度の慣れも必要です。屋外では光の加減や地面の凹凸によって誤差が出ることもあるので、あくまで目安として使うのが良いでしょう。
もうひとつのおすすめは「歩幅×歩数」で距離を測る方法です。自分の歩幅をあらかじめ測っておいて、「歩幅70cm × 28歩 = 約20m」といった計算で距離を出すことができます。歩幅がわかっていれば、道を歩きながらでもざっくりと距離がわかるので便利ですよ。特に道にメジャーを広げにくい場面などでは、この方法が役立ちます。
普段から少し意識しておくと、感覚的にも「この距離は20mくらいかな?」と予想できるようになりますよ。
20mに関する豆知識・トリビア
20mの高さ制限がある場所って?
一部の住宅地や飛行機の航路付近などでは、建物の高さが20mまでと定められている場所もあります。これは都市計画法や建築基準法に基づいており、周囲の景観や安全性を保つために設けられています。たとえば、住宅地では周囲の建物と極端な差が出ないようにするため、また日照や風通しを確保する目的もあります。
飛行機が離着陸する空港周辺では、航空法により「進入表面」や「水平表面」といった高さ制限が定められており、20mというのはその境界のひとつの目安になっていることも。建物が高すぎると飛行の安全を脅かす可能性があるため、慎重に規制が行われているのです。
他にも、文化財の近くや風致地区といった特別なエリアでは、20mという高さが景観を守る上での基準になることもあります。こうした制限は、私たちの暮らしの中に調和をもたらすための大切なルールなんですね。
ニュースや映画で使われる「20m」の話題例
ニュースなどでは、津波の高さや土砂崩れ、崖からの転落など、自然災害の脅威を伝える場面で「20m」という数字が登場することがあります。20mの津波と聞くだけで、その恐ろしさが一気に実感できますよね。高波の規模感を伝えるには、こうした数字がとても効果的に使われているのです。
また、映画やドラマなどでも、ヒーローが高いビルからジャンプしたり、巨大なモンスターが現れるシーンなどで「20mの高さ」が表現に使われることがあります。観客にスリルやインパクトを与えるために、具体的な数字を示すことで印象を深めているのです。
私たちの生活の中でも、「20m」はただの数字ではなく、驚きや緊張感、ドラマ性を伴う場面で頻繁に登場する“意味ある距離”なのかもしれませんね。
10m・30m・50mとの違いを比較してみよう
10m・20m・50mを並べて比べるとどう違う?
10mは電柱1本分くらいの高さに相当し、手を大きく伸ばして見上げたときにやっと先端が見えるような距離感です。コンビニの店舗1軒分の長さや、大型トラックの全長に近いともいわれます。
30mはおよそ9階建ての建物に相当します。地上から見上げるとかなり高く感じられ、ビルの屋上にある看板などを想像するとイメージしやすいでしょう。また、学校のグラウンドでラインを引いた時の3レーンぶん程度ともいわれています。
そして50mは、小学校のプール1周分、もしくは50m走の距離としておなじみですよね。全力で走ると10秒前後かかるこの距離は、日常では意識しづらいけれど運動の中ではよく体感される長さです。
このように並べて比べてみると、20mというのは10mよりも2倍長く、30mや50mよりは短い“ちょうどいい中間サイズ”だとわかります。決して短すぎず、かといって大きすぎない、感覚的に覚えやすい距離として使いやすいのが20mの魅力です。
「20m」が目安になる場面とは?
例えば駐車場の幅。大型のショッピングモールの駐車エリアでは、1列あたりの幅が20mほどになることもあります。車の出入りや通行スペースとしても、ちょうど余裕のある広さなんですね。
歩道橋の長さとしても20mはよく使われます。歩道橋を渡っていると「思ったより短かったな」と感じることがありますが、それがだいたい20m前後。小さな川や道路をまたぐのにちょうど良いスパンです。
また、防災の観点から「安全な避難距離」としても20mは目安になることがあります。建物から十分に離れた距離として、初動避難のラインを引く際にも意識される距離です。そう考えると、20mは日常生活の中で“安心”や“安全”をはかる単位としても重宝されているんですね。
【まとめ】20mは意外と身近にたくさんある!
この記事で「20mの感覚」はつかめた?
最初はピンとこなかった方も、たくさんの身近なものや有名な建物、スポーツの例えを通して、「ああ、なるほど!20mってこういう感じなんだ」と感じていただけたのではないでしょうか。数字だけでは分かりにくかった距離が、具体的な比較を通してぐっと現実味を帯びてきたと思います。
20mという長さや高さは、決して特別な場面だけで使われるものではなく、私たちの暮らしの中にたくさん登場しています。視覚的にも体感的にも理解が深まることで、今後は「だいたい20mくらいかな?」と自然に距離をイメージできるようになるはずです。
生活や会話で役立つ「距離感」として活かそう
20mの感覚を身につけておくと、地図を見ながらの移動計画や人との待ち合わせ、買い物中の目安など、日常のちょっとした場面でとっても役立ちます。たとえば「店の入り口からレジまでだいたい20mあるよ」など、感覚的な距離表現もスムーズになります。
また、お子さんに距離を教えたり、防災の避難距離を把握したりするときにも、20mの感覚を持っていることはとても有用です。今後、日常生活の中で「これは20mくらい?」と考えてみることで、距離感に対する理解もさらに深まりますよ。
ぜひ今日から、意識して使ってみてくださいね♪
よくある質問(FAQ)
Q1:20mの高さってどんな建物と同じくらい? → 約6〜7階建てのビルやマンションに相当します。ビルやマンションを見上げたときに、目で追うのがちょっと大変なくらいの高さです。エレベーターで6階まで上がる時間や、外から見たときの窓の並びなどを思い浮かべると、より実感しやすくなりますよ。
Q2:20mを走ると何秒くらいかかる? → お子さんなら3〜5秒、大人なら2〜3秒で走れる距離です。全力で駆け出せばあっという間にゴールしてしまうくらいの短距離ですが、走り出すタイミングやスタートの構えなども含めて考えると、ちょうど良い練習距離とも言えます。運動不足を感じたら、20mダッシュから始めるのもおすすめです。
Q3:20mって何歩くらい?目安を教えて! → 平均的な歩幅(大人で70cm)なら約28歩ほどです。歩幅は人によって異なりますが、自分の歩幅を一度測っておくと、普段の生活でも距離感をつかむのに役立ちます。「玄関から近くの電柱までが20mくらいかな?」というふうに、日常の中で試してみると面白いですよ。
Q4:小学生にもわかりやすく教えるにはどうすればいい? → 教室や校庭、身近なものにたとえてあげると伝わりやすいですよ♪ たとえば「教室5つ分の横の長さだよ」「校庭の端からベンチまでくらいだよ」といった説明が効果的です。好きなスポーツやアニメのキャラクターの大きさにたとえると、さらに楽しく覚えてもらえるかもしれません。