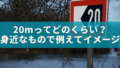「3メートル」と聞いて、すぐに長さが思い浮かびますか? 実はこの数字、私たちの生活の中にたくさん登場しているにもかかわらず、意外と感覚でつかめないものですよね。 特に女性やお子さん、普段あまり“メートル”で長さを測る機会がない方にとっては、「3メートルってどれくらい?」「高い?長い?」と戸惑ってしまうこともあると思います。
でもご安心ください。 このページでは、3メートルという長さや高さを、身近な例や体の動き、家具や道具などを使って、やさしく・丁寧に解説していきます。 読み進めるうちに、「あ、あれがちょうど3メートルだったんだ!」と納得できるようになりますよ。
そして、ただ“知る”だけでなく、日常の中で自然と“感じて覚える”ことができる内容をたっぷりご紹介。 小学生のお子さんと一緒に楽しんだり、暮らしに役立つヒントを見つけたり、きっとあなたの「距離感覚」がちょっぴりアップします。
それではさっそく、3メートルの世界を一緒にのぞいてみましょう!
3メートルの長さとは?感覚的にすぐわかる例え方

【結論】3メートル=大人の身長約1.5人分でイメージしよう
3メートルという長さは、ちょっとピンとこないかもしれませんね。
でも、身長が約160cmの女性が1人半並んだくらい、と考えるとイメージしやすくなります。
さらに言えば、160cmの人が立った状態で、もう1人がその肩に立つような感覚とも言えます。
つまり、「自分と同じ背の人がもう1人、頭の上に乗ったら」くらいの高さです。
視覚的にも想像しやすくなるので、ぜひ身近な人と並んで試してみてくださいね。
ジャンプしても届かない距離|感覚で捉える3mの長さ
3メートルは、高くジャンプしても届かないくらいの距離です。
お部屋の天井よりもずっと高く、運動会で使う竹馬でもなかなか届かないほどです。
実際、日本の住宅の天井は2.4m程度なので、それより60cm以上も高いことになります。
バレーボールのネットよりもずっと上なので、「かなり高いな」と感じるはずです。
スポーツ選手でも届かない高さと考えると、日常ではなかなかお目にかかれないかもしれませんね。
メートルに慣れていない人向け!簡単なサイズ換算のコツ
「メートルってなじみがないな…」という方には、身近なもので考えるのが一番です。
例えば、1メートル=100センチなので、100センチの定規を3本並べたら3メートルです。
他にも、お掃除でよく使うクイックルワイパーの柄はだいたい1メートルくらい。
これを3本並べた長さ、と考えてみるとわかりやすいですね。
家具のサイズ表示やお洋服の布地など、生活の中で「1メートル」という単位を意識すると、自然と感覚がついてきますよ。
高さで感じる3メートル|建物・設備・スポーツで比較

バスケットゴールの高さ(3.05m)はまさに実例
バスケットボールのゴールの高さは約3.05メートル。
テレビで試合を見ると、選手たちがその高さにボールを入れているのがよくわかります。
さらに言うと、このゴールの高さは中学・高校・プロの試合でも共通しており、世界基準でもあるんですよ。
ゴールにボールをシュートする際、選手たちはジャンプと腕の伸びを合わせて、ようやく届くほど。
この3.05メートルの高さが、スポーツ選手の身体能力をより一層引き立てているのですね。
バスケットボール観戦をしながら「今のジャンプでどれくらい上がってるんだろう?」と想像するのも楽しいかもしれません。
マンション2階のベランダはちょうど3メートル前後
一般的なマンションの2階部分のベランダの床までが約3メートル。
お住まいの建物を見上げてみると、身近な例として想像しやすいですね。
実際に外出したときに、2階建ての建物を見上げてみてください。
1階と2階の間には階段や配管などもあるため、建築基準上およそ2.8〜3.2メートル前後の高さになります。
近くに同じくらいの建物があるなら、目線で距離感をつかむ練習にもなりますよ。
また、ベランダの柵や外壁のデザインを比べてみると、どの程度の高さ感かよりはっきりとわかります。
電柱の下半分・街中でよく見る3mの高さ
電柱の高さは通常9〜10メートル。
その下半分くらいが、だいたい3メートルになります。
つまり、電柱の真ん中あたりを見上げると、それがちょうど3メートル程度ということです。
街中を歩いているときに、「この看板、電柱のどのあたりまで届いているかな?」「この標識の上端は3メートルを超えている?」など、ちょっとした観察ゲームのように見ると楽しいですよ。
また、電柱の周りには配線や変圧器、照明なども取り付けられていて、それぞれの高さも違います。
こうした街の設備を観察することで、3メートルという高さがいかに高いかを感覚的に理解することができます。
さらに、街灯やバス停の屋根など、身近な構造物と比べてみるのもおすすめです。
「この街灯は自分よりどれくらい高いかな?」と考えるだけで、日常の中で自然と距離感が身につきますよ。
3メートルの高さに関する注意点(頭上注意・標識など)
駐車場やトンネルの入り口などで「高さ制限3.0m」と表示されていることがあります。
これは大型車が通れるかどうかの目安になっているんですよ。
特に車を運転される方や、荷物を積んだトラックなどに関わるお仕事をされている方は、この高さ制限に注意する必要があります。
うっかり高さを超えてしまうと、屋根をぶつけてしまったり、事故につながる危険もあるんです。
また、看板やガード下にも3メートルの制限表示がされていることが多いので、普段の生活の中でも気をつけて見ておくと良いですね。
「ここって何メートルあるんだろう?」という目で街を見渡すだけで、距離感のトレーニングにもなりますよ。
長さで測る3メートル|家具・道具・紙で再現してみよう

A3用紙7枚+1円玉3枚で3mをピッタリ再現
A3サイズの用紙(約42cm)を7枚横に並べて、その間の小さなすき間を1円玉(直径2cm)でちょこちょこっと埋めていくと、なんとぴったり3メートルになります。
この方法はとても手軽で、家にA3用紙と1円玉があればすぐにできるので、お子さんと一緒に「3メートルってどれくらい?」を体験するのにもぴったりです。
実際に並べてみると、意外と長いと感じるかもしれません。
「え、3メートルってこんなにあるの?」と驚かれる方も多いんですよ。
紙を使うことで、数字だけでなく目で見て、触って実感できるので、距離感を覚えるのにとても役立ちます。
横断歩道の白線1本分=ほぼ3mという意外な事実
実は、横断歩道の白い線1本の長さが、約3メートルあるんです。
信号待ちをしているときや、歩道を渡るときにふと足元を見てみると、「この白線って結構長いな」と気づくことがあります。
特に普段は気にせず歩いてしまう部分なので、そうした場所に3メートルが潜んでいると思うと、ちょっとした発見になりますよね。
「今、自分は3メートルの上を歩いてるんだな」と思うだけで、身近な景色が少し違って見えてくるかもしれません。
こうした身近な場所での“距離感トレーニング”も、生活をちょっと楽しくしてくれるコツになります。
3メートル級の家具(ソファ・ラグ)で実感するサイズ感
3人掛けの大きなソファや、リビング用のラグマットの長辺が約3メートルになることがあります。
家具売り場で実際に見ると、その存在感に驚くかもしれません。
「思ったより大きい!」と感じることが多く、3メートルという長さがいかに広いかを実感できます。
ラグであれば、3メートルの長さがあれば大人が足を伸ばして寝転んでも余裕がありますし、お子さんが何人か集まってもゴロゴロできるスペースになります。
また、ソファの場合は、座るだけでなく、横になってくつろげる余裕があり、家族みんなで使えるサイズ感です。
さらに、こうした大型家具は引っ越し時や配置換えの際に「通路に入るか」「搬入できるか」などを確認するための基準としても使えます。
3メートルの家具がどれくらいのスペースを必要とするかを把握しておくことで、インテリア選びがぐっとスムーズになりますよ。
棒状の道具(釣竿・物干し竿)で測る方法も便利
3メートルの釣竿や物干し竿も一般的。
実際に目にすると、「ああ、これが3メートルか」と実感できます。
釣具店やホームセンターでよく見かけるこれらの道具は、長さが明記されていることが多いため、目で見て3メートルを感じるのにとても便利なアイテムです。
たとえば、釣竿を広げたときの長さを地面に沿って並べてみると、かなりの距離があることに驚くかもしれません。
また、物干し竿は室内用・屋外用ともに3メートル前後のものが多く、毎日の洗濯で自然とその長さに触れている方も多いのではないでしょうか?実際に手で持って運んだり設置したりするなかで、「これが3メートルなんだな」と感覚が身についていきます。
生活の中でこうした道具に注目してみると、よりリアルに3メートルを捉えられるようになりますよ。
体のパーツで測る3メートル|手・腕・歩幅で簡単目測術
両腕を広げると約1.5m|2人で3mを再現しよう
大人が両腕を広げた長さは、だいたい身長と同じくらい(約1.5m)。
2人で並んで手を広げると、3メートルを簡単に作れます。
この方法はとてもシンプルでわかりやすく、お子さんや友人と一緒に試すのにもぴったりです。
例えば、家族で「ちょっと3メートル測ってみよう」と並んでみるだけでも、距離感を体で覚えるきっかけになりますよ。
横並びに立って両腕を思いっきり広げるだけで、「これが3メートルか!」という感覚をつかめるので、道具が何もなくてもOKです。
さらに、鏡の前や広めの廊下などを使うと、その感覚がよりはっきりとします。
「1人分はこれくらい、2人分はここまで」と線を引いたり、印をつけたりすれば、繰り返し見ることで自然に距離が身についてきます。
歩幅で3mを測るには?実際に何歩必要か検証
女性の歩幅はおよそ60〜70cm。
つまり、3メートルを歩くには4〜5歩ほど。
お部屋の中でも気軽に測れます。
実際にフローリングの上や廊下などで歩いてみると、より実感しやすくなりますよ。
普段の歩き方で「ここからここまでが3メートルなんだ」と体で覚えておくと、お出かけ先や買い物中にも役立ちます。
また、歩幅は人それぞれ違うので、自分自身の歩幅を一度測ってみるのもおすすめです。
たとえば、1メートルのメジャーを使って「自分の1歩が何cmか」をチェックしてみましょう。
その数値がわかれば、「じゃあ3メートルは何歩分だな」と簡単に換算できます。
ちょっとした運動やストレッチにもなるので、楽しみながら距離感を学べる一石二鳥の方法です。
手のひら・指・腕の長さを積み重ねて3mを作る方法
自分の手のひら(約15〜18cm)を何回分並べれば3メートルになるか…ちょっとした遊び感覚で楽しめます。
例えば15cmの手のひらなら、20回分で3メートルになります。
手のひらを実際に机の上や床に沿って何度も置いて、3メートルを「測る」のではなく「感じる」ことができるのが面白いところです。
また、指の長さでも試してみると新たな発見があります。
人差し指の長さは大体7〜8cmほどなので、それを40回分くらいで3メートルに。
少し根気のいる作業ですが、子どもと一緒に「指を何本分で3メートル?」なんて遊びながら覚えるのも楽しいですね。
腕の長さ(肩から手首まで)も大人なら50〜60cmある場合が多いので、5〜6回分をつなげると3メートル近くなります。
このように体の部位を基準にすると、何も道具がなくても測れるという安心感があります。
普段から「これは手のひら何枚分かな?」と考える癖をつけておくと、自然と距離感が身につきますよ。
腕立て伏せの姿勢で測る3m感覚トレーニング
うつ伏せになって手足をまっすぐ伸ばした長さを1.5mとすれば、2人分で3メートル。
体を使って感覚を覚えるのもおすすめです。
この方法は特別な道具がいらず、体ひとつで感覚を掴めるのが魅力です。
実際にフローリングの上やヨガマットの上で試してみましょう。
1人が腕立て伏せの姿勢になり、もう1人がその隣に並んで同じ姿勢になると、およそ3メートルになります。
このとき、2人の間に少しすき間を空けたり、ぴったりくっついてみたりと、調整しながら正確に3メートルを再現するのも、ちょっとしたゲーム感覚で楽しいです。
小さなお子さんでも「ママとパパが並ぶとこれくらいなんだ」と視覚的に理解しやすくなりますし、ちょっとしたストレッチや運動にもなるので一石二鳥ですね。
また、1人でやる場合も壁に印をつけたり、スマホのカメラで撮影してあとから比較してみると、意外と正確に測れていることに気づくかもしれません。
日常生活で3メートルを使うシーンとは?用途・距離感をチェック
室内で3mが必要な場面(カーテン・ケーブル・布など)
窓にカーテンをつけるときや、大きなテーブルクロス、長めの延長コードが必要なとき、3メートルがちょうどよく使われます。
例えば、掃き出し窓にカーテンをかけるとき、レールの幅が2.5メートルを超えることがよくあります。
その際には、カーテンの生地は余裕を持って3メートル以上必要になります。
また、ドレープが美しく見えるように布地を多めに取ることも多いため、実際に必要な長さはさらに長くなることも。
延長コードの場合も、デスクとコンセントの距離が2メートルを超えることが多いため、3メートルのコードがとても重宝します。
キッチン家電や掃除機を使うときなど、動きながら使う場面では特にありがたい長さですよね。
さらに、大きなテーブルにクロスをかけたり、布を使ってカバーやカーテン、パーテーションを作ったりする際も、3メートルという長さは非常に実用的です。
生地屋さんで「3メートルください」と言うと、たいていの家庭用サイズに対応できます。
屋外で使う3メートル(スポーツ・DIY・駐車場など)
バドミントンのネットの高さや、自転車用のテント、駐車場の幅などにも3メートルが登場します。
意外と日常の中にある距離です。
スポーツでは、特に屋外の設営時に3メートルの感覚が大切になります。
たとえば、バドミントンネットの支柱の高さが約1.55メートルで、両側の間隔が6メートルほど。
その半分である3メートルは、ネットの半分の位置を取るときなどに役立ちます。
また、アウトドアで使うテントの横幅やタープの張り出しの長さも3メートル前後のものが多く、設置スペースを測るときの目安になります。
車1台分の駐車スペースの幅もだいたい2.5〜3メートルなので、ガレージやカーポートの設計にも3メートルという単位がぴったりです。
DIYで物置やウッドデッキを作るときにも、3メートルの木材やパイプが標準サイズとして流通しているため、設計や材料選びの基準にもなります。
こうして見てみると、3メートルは屋外でも本当に活躍するサイズですね。
子どもに「3メートルってどれくらい?」と聞かれたときの説明法
「ママとパパが横に並んで手を広げたくらいだよ」「バスケットのゴールくらいだよ」と伝えると、子どもにもわかりやすいですね。
さらに、遊びの中で一緒に3メートルを体感してみるのもおすすめです。
例えば、紐やメジャーを使って3メートルの長さを床に広げ、「このくらいが3メートルだよ」と実際に見せてあげると、よりイメージしやすくなります。
お部屋の中に「3メートルゾーン」を作って、おもちゃを並べたり、ジャンプして届くかチャレンジしてみたりと、遊び感覚で覚えられると楽しいですね。
また、「おうちの窓のカーテンの横幅が3メートルくらいあるよ」「テレビボードの長さがこのくらい」など、子どもが普段見ているものと結びつけると、さらに理解が深まります。
こうした会話の積み重ねで、子どもたちは自然と距離感を身につけていきます。
3メートル以内で注意したい生活の危険(ペット・運転・子ども)
3メートル以内は、犬のリードの長さや、自転車の急ブレーキ時の停止距離など、注意が必要な場面が多いです。
安全の目安にもなります。
例えば、お散歩中のワンちゃんのリードが3メートルだと、急に飛び出したときに周囲にぶつかったり、車道にはみ出してしまったりする危険があります。
そのため、飼い主さんは常に3メートルの範囲を意識して行動することが大切です。
また、自転車や自動車では、ブレーキをかけてから完全に止まるまでに3メートル以上かかることも。
特に雨の日や滑りやすい路面では、その距離はさらに長くなります。
3メートル以内に人や障害物があった場合、衝突の危険があることを意識するだけでも、事故を防ぐ大きな一歩になります。
子どもに関しても、目を離したすきに3メートル先へ走っていってしまうこともよくあります。
公園や広場では、子どもが3メートル以内にいるかを常に意識することで、安心して遊ばせることができます。
他の単位で見る「3メートル」|フィート・インチ・ヤード・センチで換算!
3メートルはフィート・インチで何?海外単位に換算してみた
3メートルは約9.84フィート、約118.11インチです。
海外では長さをフィートやインチで表すことが多いため、旅行先での買い物や建築図面の読み取りにとても役立ちます。
たとえば、アメリカやイギリスの家具通販サイトでは、ソファやテーブルのサイズがインチやフィートで書かれていることが多くあります。
そのとき、「3メートル=約118インチ」と知っていれば、自分の部屋に置けるかすぐに判断できますね。
また、身長や身の回りの長さも換算しておくと、英語圏の人と話すときの話題にもなって便利です。
センチやミリ、ヤードなどでも3mを感覚的に知ろう
3メートルは300センチメートル、3,000ミリメートル、約3.28ヤードに相当します。
センチメートルやミリメートルは日本でも馴染み深く、文房具や洋裁、工作などでもよく使われる単位ですね。
一方、ヤードはアメリカやイギリスなどで主に使われる単位です。
例えば「1ヤードは約91.44センチ」と覚えておくと、3ヤード=約2.74メートルなので、「あ、3ヤードってだいたい3メートルくらいだな」とイメージできます。
こうした単位感覚を持っておくと、世界中のいろんな情報が読み解きやすくなりますよ。
単位換算を覚えるコツとおすすめアプリ紹介
「単位変換ってなんだか難しそう…」という方におすすめなのが、スマホやタブレットで使える無料の単位換算アプリです。
「単位変換ツール」や「メジャーアプリ」などで検索すれば、すぐにダウンロードできるものがたくさんあります。
アプリを使えば、「3メートルってフィートで何?」「ヤードでは?」といった疑問にもすぐ答えが出せます。
お買い物中や海外旅行のときにも活躍しますし、お子さんの勉強にも役立つので、1つ入れておくと便利ですよ。
中にはAR機能付きで、実際の空間に長さを投影できるようなアプリもあるので、楽しく学べておすすめです。
【図解付き】3メートルを目で見て理解しよう|画像・イラストで徹底比較
3メートルの高さ・長さを写真で比較してみよう
写真で見ると、3メートルの高さや長さが一目瞭然。
文章だけでなく視覚でも覚えられます。
図解でわかる!身近なモノとの「3m比較イラスト」
「冷蔵庫2台分」「車1.5台分」など、身近なもので3mを図解すると、とってもわかりやすくなります。
SNSでバズった「◯◯って3メートルあったの!?」画像まとめ
SNSには「意外と3mあるもの」がたくさん。
バズった画像を見て「へぇ〜!」と楽しむのもおすすめです。
【雑学】3メートルにまつわる豆知識&意外な使い道
3メートル以上ある魚や動物って?
ジンベエザメやシロナガスクジラの赤ちゃんなど、3メートルを超える生き物も。
ジンベエザメは成魚で10メートル以上になることもありますが、3メートル前後の若い個体でもすでに人間よりはるかに大きく、その迫力に圧倒されます。
また、シロナガスクジラの赤ちゃんは生まれたときからすでに7メートルほどあると言われており、3メートルという大きさは海の世界では「まだ小さい」とされることも。
ほかにも、大型のワニやアナコンダ、シュモクザメなども3メートルを超える種類が存在します。
動物園や水族館で3メートル級の生き物を見ると、自然界のスケールの大きさを改めて感じられますよ。
3メートル制限のトンネル・標識の意味と注意点
「高さ制限3.0m」と書かれた標識は、大型車やトラックに向けたもの。
私たちが車を運転する際も意識すると安全です。
特にキャンピングカーや自転車を積んだ車、高さのあるキャリア付きの車などは、うっかり高さ制限を超えてしまうこともあります。
トンネルや高架下、立体駐車場の入り口などに表示されているこの標識は、運転者にとってとても重要な目印です。
また、高さ3メートルの制限は構造物だけでなく、時には低く垂れ下がった木の枝や仮設看板などでも問題になることがあります。
事前にルートを確認し、表示に注意して運転することで、思わぬ事故やトラブルを未然に防ぐことができます。
日頃から「3メートルの高さってどのくらい?」という感覚を身につけておくと、より安全な運転につながりますね。
映画や漫画で登場する「3メートル」のシーンまとめ
映画の怪獣やロボットが「全長3メートル」などと紹介されることも。
作品を通じてスケール感を楽しめます。
例えば、SF映画や特撮作品では、「全長3メートルのロボットが出現」などという設定がよく登場します。
人間と並ぶとその巨大さが際立ち、物語に迫力を与えています。
人気漫画の中でも「3メートル級の巨人」や「3メートルの翼を持つキャラクター」など、印象的な存在が多く描かれています。
アニメでも、主人公が対峙する敵キャラが「体高3メートル」と紹介されることがあり、画面を通してその大きさを感じ取ることができます。
ファンタジーの世界では、この3メートルという数字が「非日常」や「強さ」を象徴することも多く、ストーリーの中で非常にインパクトを持っています。
観る人にとっても、「3メートルってどれくらい?」という疑問が湧きやすく、実生活での距離感と照らし合わせて考えるきっかけになりますね。
【Q&A】3メートルに関するよくある質問に答えます!
3メートルってジャンプして届く?
普通のジャンプでは届きません。
オリンピック選手でも垂直ジャンプの記録は1メートル前後が限界とされているため、3メートルという高さは、日常的にはまったく手が届かない領域なんです。
例えば、垂直にジャンプしても、腕を思いきり伸ばしても2メートル少し届くかどうかが一般的。
そのため、3メートルの高さは、まさに「見上げる世界」と言えるでしょう。
バスケットゴールにジャンプしてボールを入れる選手の姿を見ると、その高さに届くことの難しさがよくわかりますね。
家の天井や部屋の照明が約2.4メートルなので、それよりもずっと高く感じられるのも納得です。
3メートルの物干し竿はどこで買える?
3メートルの物干し竿は、ホームセンターや大型の生活雑貨店、またはAmazonや楽天といった通販サイトでも手軽に購入できます。
種類も豊富で、伸縮式やステンレス製、軽量タイプなど用途に応じて選べます。
ただし、3メートルという長さは運搬時に少し注意が必要です。
車で運ぶ場合、軽自動車やコンパクトカーでは入りきらないこともあるので、店舗で購入する際は配送サービスを利用するのが安心です。
また、通販で購入する場合は、梱包サイズや配送方法を確認しておくと安心ですよ。
お住まいのベランダや物干しスタンドのサイズも事前に測っておくと、ぴったりの長さを選びやすくなります。
3mの長さを感覚で覚えるコツは?
3メートルの長さを感覚でつかむには、日常の中で「これは3メートルくらいかな?」と意識することがポイントです。
たとえば「大きめのソファ1台分」「歩幅で5歩分」「2人分の両腕を広げた長さ」など、自分なりの基準を持っておくと、さっと距離をイメージしやすくなります。
また、道や廊下など身近な場所で実際に3メートルを測ってみるのも効果的です。
100円ショップで売っているメジャーやロープを使って「ここからここまでが3メートル」と体感しておけば、自然と距離感が身につきます。
さらに、よく見る標識や建物の一部などを目印に「これがだいたい3メートルなんだ」と認識しておくのもおすすめです。
毎日の生活の中で少しずつ距離感を意識していくと、「3メートルってこんな感じ」と自然に覚えられますよ。
まとめ|3メートルの長さ感覚を身につけるには?
数値で理解→感覚で納得→生活で実感しよう
3メートルという長さをただの数字で覚えるのではなく、実際に見たり触ったりすることで「なるほど、これくらいなんだ」と体で納得することがとても大切です。
日常生活の中で「3メートル」が登場する場面を意識してみると、だんだん距離感が自然と身についてきます。
視覚的に見えるもの、感覚で感じるもの、実際に動いて測るもの——それらを総合的に体験することで、数字と現実がしっかり結びついていくのです。
目測力を鍛えれば生活の質が上がる!
「この距離、どれくらいかな?」とすぐに見て判断できる目測力があると、日常生活でとても便利です。
例えば家具を買うとき、部屋に置けるかどうかをパッと判断できたり、カーテンやラグのサイズを選ぶ際に迷わず決められたりします。
DIYやガーデニングを楽しむ人にとっても、正確な距離感は作業の効率を上げ、無駄を減らすポイントになります。
また、子どもとの遊びや安全確保の場面でも役立ちます。
公園で「ブランコとベンチの間は3メートルくらいかな」と距離を測ったり、車の運転中に「この高さは大丈夫?」と瞬時に判断できるようになると、安心感もぐっと高まります。
目測力は一朝一夕では身につきませんが、少しずつ日常の中で意識することで、確実に鍛えられていきますよ。
「3メートル=◯◯」と自分なりの基準を作って覚える
「3メートルってどれくらい?」と聞かれたときに、自分だけの基準があるととても便利です。
「うちのリビングの壁から壁までがちょうど3メートル」「いつも座っているソファの長さがそれくらい」など、生活の中のものを基準にすると覚えやすく、忘れにくいんです。
また、お気に入りの洋服を干すときに使う物干し竿の長さや、通学路の横断歩道の白線の長さなど、日常でよく目にするものを「これは3メートルだな」と覚えておくと、他の距離を考えるときにも応用がききます。
人によって基準にしやすいものはさまざまなので、「これは自分にとっての3メートル」と感じるものを1つ見つけてみてくださいね。
それが、距離感を確かなものにしてくれる大きな手助けになります。